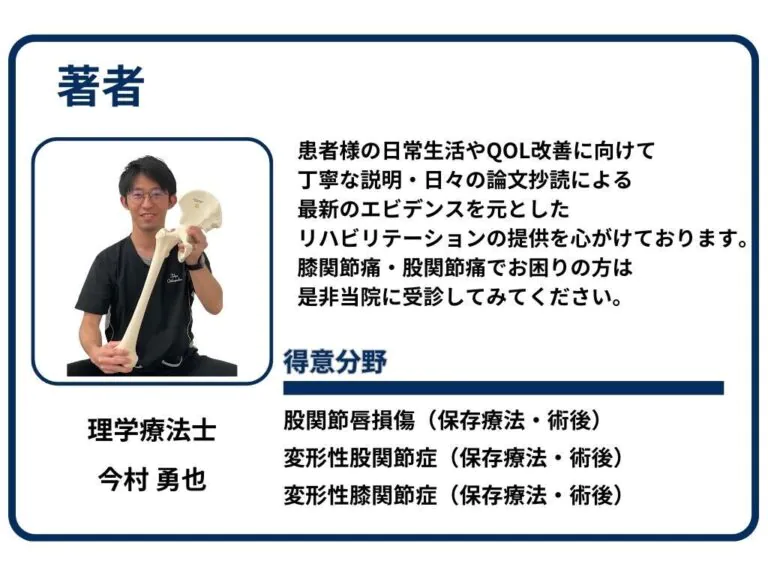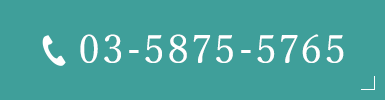変形性膝関節症は膝になぜ水がたまる??:原因から治療・予防まで
今回のkey point
| 変形性膝関節症は、炎症により関節を栄養する滑液の産生が過剰になり、結果的に関節内に水がたまる |
| 膝に水が溜まった場合の対処として、冷却や炎症止め薬や注射による関節穿刺などがある |
変形性膝関節症と関節水腫(水がたまる)の関係:原因から治療・予防まで
膝が痛く腫れて「水がたまる」と言われたことはありませんか?これは多くの場合、変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)という膝関節の病気に伴って起こる症状です。
今回は、変形性膝関節症とはどんな病気なのか、なぜ膝に水がたまる(関節水腫)状態になるのか、そのメカニズムや治療法・予防法について、最新の知見も交えながらわかりやすく解説します。
変形性膝関節症とは何か(原因・症状・進行過程)
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨が長年の使用によってすり減り、関節に痛みや変形をきたす疾患です。主に中高年に多く見られ、高齢の女性に特に多いことが知られています。
膝の表面を覆う軟骨はクッションの役割を果たしていますが、加齢や膝への負担(肥満や過去のケガなど)によって少しずつ磨り減っていきます。一度すり減った軟骨は自然には元に戻らないため、時間をかけて徐々に進行し、関節の変形や痛みが悪化していきます。
症状として初期の段階では、膝の違和感や動かしにくさ、立ち上がりや歩き始めの際の軽い痛みから始まります。特に階段の昇り降り(特に下り)や正座などで膝に痛みを感じることが多く、休めば治まる程度です。
しかし病気が進行すると痛みは徐々に強くなり、長時間の歩行や立ち仕事でも痛むようになります。
また、膝に炎症が起きると腫れて膝に水がたまる状態(関節水腫)になり、膝が重だるく感じられることもあります。炎症による腫れのため膝周囲が熱っぽく感じることもあります。
さらに関節の変形が進むと、膝がO脚やX脚に変形し、関節の曲げ伸ばしが制限されていきます。末期には軟骨がほとんど無くなり骨同士が擦れ合う状態となるため、安静にしていても痛みが出たり、膝の不安定感(ぐらぐらする感じ)を生じ、日常生活に支障を来すことがあります。
変形性膝関節症は非常に一般的な疾患で、中年以降では症状の有無にかかわらず25〜40%の人が罹患しているとも言われます。高齢化社会に伴い患者数は今後さらに増加すると考えられています。
関節水腫(膝に水がたまる)とは何か
膝が「腫れて水がたまる」と表現される状態は、医学的には「関節水腫」(かんせつすいしゅ)と呼ばれます。
簡単に言えば、関節内にある滑液(関節液)が過剰に溜まった状態です。
膝関節には正常な状態でも約1〜3ml程度の少量の関節液が存在し、軟骨に栄養を与え関節の動きをなめらかにする潤滑油の役割を果たしています。この関節液は関節を包む滑膜(かつまく)という膜によって常に新陳代謝されており、古い液を吸収して新しい液を分泌するバランスが保たれています。
しかし、何らかの原因で関節に炎症が起こると滑膜の働きが乱れ、必要以上に滑液が分泌されてしまいます。
その結果、関節腔に液体がどんどん溜まって膝が腫れ上がるのです。炎症が強い場合は関節液の量が30ml以上になることもあり、膝がぱんぱんに膨れて曲げ伸ばしが困難になります。
関節液自体は淡黄色透明の液体で(水道水や真水が溜まっているわけではありません)、炎症の程度によって粘り気や色が変化することもあります。
膝に水がたまると、膝関節は見た目にも腫れぼったく膨らみます。関節内部の圧力が高まるため痛みが生じ、膝を動かすと痛みが増すほか、ひどい場合は安静時にもズキズキ痛むことがあります。また、関節液が溜まっていることで膝が突っ張った感じになり、可動域が制限されて十分に曲げ伸ばしできなくなります。炎症によって患部に熱感(ほてり)を感じることも多いです。患者さんは「膝が重だるい」と表現することもあります。
関節水腫は変形性膝関節症に伴うことが多いですが、原因はそれだけではありません。たとえば半月板の損傷や靭帯損傷などのケガ、関節リウマチなどの炎症性疾患、痛風などによる結晶の沈着、感染症など、膝関節に炎症を起こす様々な状況で膝に水がたまることがあります。そのため、膝に水が溜まった場合は単に水を抜くだけでなく原因を特定することが重要です。
変形性膝関節症と関節水腫の関係(なぜ変形性膝関節症で水がたまるのか)
変形性膝関節症では、なぜ膝に水(関節液)がたまりやすいのでしょうか。そのキーワードは「炎症(滑膜の炎症)」です。
変形性膝関節症は単なる加齢による“摩耗”の病気と思われがちですが、近年の研究では、たとえ初期の段階でも関節内部で滑膜炎(関節包の内側の膜の炎症)が起こりうることがわかっています。
変形性膝関節症は軟骨だけでなく関節全体の疾患であり、滑膜が炎症を起こすと厚く肥大化したり滑液の産生が過剰になったりして、結果的に関節内に水がたまる原因になります。
実際、ある研究では膝に痛みがある変形性膝関節症患者の約55%に中等度から大量の関節水腫が認められたと報告されています。この炎症(滑膜炎)は膝の痛みや可動域低下、筋力低下とも関連しており、膝に水がたまると痛みで太ももの筋肉(大腿四頭筋)が弱ってしまうなどの悪循環が生じます。
では、なぜ滑膜に炎症が起こるのかというと、変形性膝関節症で進行した関節では様々な刺激因子が存在するためです。
例えば、軟骨がすり減った際に出る軟骨の破片や、骨同士がこすれあって生じる微細な骨片などが関節内に散らばると、それらが滑膜を刺激して炎症反応を引き起こします。
実際、軟骨組織がすり減ると、その削れたかけらが滑膜を刺激し、膝に水がたまりやすくなることが指摘されています。これは、関節内に生じたゴミや異物を排除しようとする身体の防御反応でもあります。
また、変形性膝関節症の膝は構造的に不安定になりやすく、過度の使用などでも炎症が誘発されます。例えば長時間の歩行や階段昇降、重い物を持って立ち続けるといった動作は、軟骨のすり減った膝関節に大きな負担をかけ、炎症と関節水腫の誘因となります。こうした負荷がかかったとき、膝は自らを守るために滑液を増やしてクッションを作ろうとしますが、結果的に水がたまって腫れることになります。このように変形性膝関節症そのものが関節内の炎症を引き起こし、水がたまる原因になるため、両者は切っても切れない関係にあります。
関節水腫の治療方法(保存療法、穿刺、リハビリなど)
膝に水がたまった場合の治療は、まず原因に対処することが大切です。変形性膝関節症に伴う関節水腫であれば、基本は保存療法(手術をしない治療)で炎症を抑え、痛みや腫れを和らげることになります。一般的な治療法は次の通りです。
-
安静と冷却(RICE処置):
急性期(腫れが強く痛むとき)には、膝を安静にして冷やすことが基本です。安静により関節への負担を減らし、氷嚢や冷湿布で冷却することで血管を収縮させて腫れと痛みを抑えます。痛みが強い場合は膝を心臓より高く上げて安静にすると、腫れの軽減に役立ちます。 -
薬物療法:
炎症と痛みを抑えるために、消炎鎮痛剤(NSAIDs)がよく使われます。内服薬や座薬のほか、胃に負担をかけたくない場合は外用薬(湿布や塗り薬)も有効です。また腫れが強い場合、医師が判断してステロイド(副腎皮質ステロイド薬)を短期間使用することもあります。ステロイドは強力に炎症を抑える効果があり、関節内に直接注射(関節内注射)することもあります。ただし頻用は副作用のリスクがあるため注意が必要です。 -
関節液の穿刺・吸引:
膝に溜まった水が多く、腫れと痛みがひどい場合は、病院で関節穿刺(関節に針を刺して液を抜く処置)を行います。穿刺によって関節内の圧力が下がり、痛みや膝の張りが即座に軽減します。抜いた液体を調べれば感染の有無や結晶(痛風など)、炎症の程度を知ることができ、原因の特定にも役立ちます。ただし、水を抜くこと自体は一時的な対策であり根本的な治療ではありません。変形性膝関節症が治らなければまた水がたまる可能性が高いため、あくまで症状緩和と診断のための処置と考えます。また、関節に針を刺す行為にはわずかながら感染症のリスクもあるため、適切な衛生環境で医師に行ってもらう必要があります。 -
リハビリテーション(運動療法):
痛みと腫れが少し落ち着いたら、リハビリによる機能回復を図ります。具体的には理学療法士の指導のもとで大腿四頭筋を中心とした筋力訓練やストレッチ、関節可動域訓練などを行います。太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)は膝関節を支える重要な役割があるため、ここを鍛えると関節への負担が減り再発予防につながります。また、痛みで固くなった関節をほぐすことで可動域を改善し、日常生活の動作(立ち上がりや階段昇降など)の改善を目指します。リハビリは最初痛みが出ない範囲で始め、徐々に強度を上げていきます。 -
装具療法:
膝に負担をかけないよう、膝サポーターを用いて関節を安定させたり、必要に応じて杖の使用を検討します。靴の中敷き(足底板)でO脚やX脚の負担を調整することもあります。適切な装具の使用は痛みの軽減と日常生活での安定に役立ちます。 -
手術療法:
保存療法で改善しない重度のケースや、半月板の断裂・靭帯損傷など明らかな器質的損傷が原因で水腫を繰り返す場合、手術が検討されることもあります。変形性膝関節症そのものの根治には人工膝関節置換術などの手術がありますが、水腫に対していきなり手術を行うことは稀です。まずは上述の保存的な治療を十分に行い、それでも痛みで生活がままならない場合に限り検討されます。
関節水腫の予防法(日常生活でできる工夫)
膝に水がたまるのを防ぐには、膝関節に炎症を起こさせない/負担をかけすぎないことが大切です。
変形性膝関節症の進行予防とも共通しますが、日常生活で次のような工夫を心がけましょう。
-
適切な体重管理:
体重が重いと膝関節への負担も大きくなるため、肥満を予防・改善することは膝の水腫予防の基本です。標準体重への減量によって膝への負荷が軽減され、炎症が起こりにくくなります。また、糖尿病などの生活習慣病があると炎症体質になりやすいので、食生活を見直し健康管理に努めましょう。 -
運動と筋力維持:
膝周りの筋肉を鍛えることで関節を安定させ、衝撃を和らげることができます。特に太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることは効果的で、大腿四頭筋訓練(脚上げ運動など)やウォーキングを無理のない範囲で継続しましょう。運動習慣は関節の栄養循環も促進し、軟骨の代謝にも良い影響を与えます。ただし、運動は少しずつ段階的に負荷を上げることが大切です。一念発起して急に激しい運動を始めると膝に過度なストレスがかかり、かえって炎症を誘発する恐れがあります。運動前には準備体操やストレッチで関節と筋肉を温め、怪我と炎症の予防をしましょう。 -
膝に負担をかけない工夫:
日常動作の中で膝に過度な負荷がかからないよう意識します。例えば、重い荷物を持つときはできるだけ台車を使う、持つ場合も身体に近づけて膝への負担を減らす、長時間の中腰姿勢(前かがみでの作業)は避ける、といった工夫です。和式の生活では深く膝を曲げる場面が多いですが、正座や長時間の膝立ちは極力避けるようにします。どうしても床に座る必要があるときは、低めの椅子や正座椅子を利用して膝を守りましょう。また、靴にも注意が必要です。クッション性の高い靴やインソールを用いることで膝への衝撃を和らげることができます。ヒールの高い靴や底の硬い靴は膝に負担がかかるため、日常使いでは避けると良いでしょう。 -
低負荷エクササイズの活用:
膝に水がたまりやすい人でも続けやすいのが、水中での運動です。プールでのウォーキングや水中エアロビクスは、浮力によって膝への荷重を軽減しつつ筋力を鍛えることができます。関節への衝撃が少ないため痛みが出にくく、しかも全身の有酸素運動にもなるので減量効果も期待できます。
以上のような対策で膝のコンディションを整えることが、結果的に関節水腫の予防につながります。普段から膝に違和感を覚えたら無理をせず休ませる、早めに膝用サポーターを使うなど、膝と上手に付き合っていくことが大切です。
まとめ
変形性膝関節症は、膝の関節軟骨がすり減ることで生じる慢性の関節疾患で、多くの高齢者が悩まされています。進行に伴い関節に炎症が起こりやすくなり、その結果として膝に水がたまる関節水腫が発生します。膝に水がたまるのは体からの「膝に炎症が起きているよ」というサインとも言えます。関節水腫そのものは水を抜けば一時的に楽になりますが、根本には変形性膝関節症などの原因がありますので、原因への対処と再発予防が重要です。
幸い、滑膜の炎症(滑膜炎)は適切な保存療法で鎮めることができます。痛みや腫れがあるときは無理をせず安静にし、必要に応じて医療機関で水を抜いてもらいましょう。早期に治療すれば症状の悪化を防ぎ、関節の破壊を抑えることができます。また、日頃から体重管理や筋力トレーニングを行い、膝に負担をかけすぎない生活を心がけることが最大の予防策です。最新の研究でも、変形性膝関節症でみられる滑膜炎を抑えることで痛みが軽減し関節機能が改善する可能性が示唆されています。膝の痛みや腫れを感じたら放置せず、早めに当院を受診して適切な対処を受けてみましょう。
参考文献
・Elsawy NA, Ibrahiem AH, Younis GA, Meheissen MA, Abdel-Fattah YH. Clinical examination, ultrasound assessment and aspiration of knee effusion in primary knee osteoarthritis patients. J Orthop Surg Res. 2023 Jun 10;18(1):422.