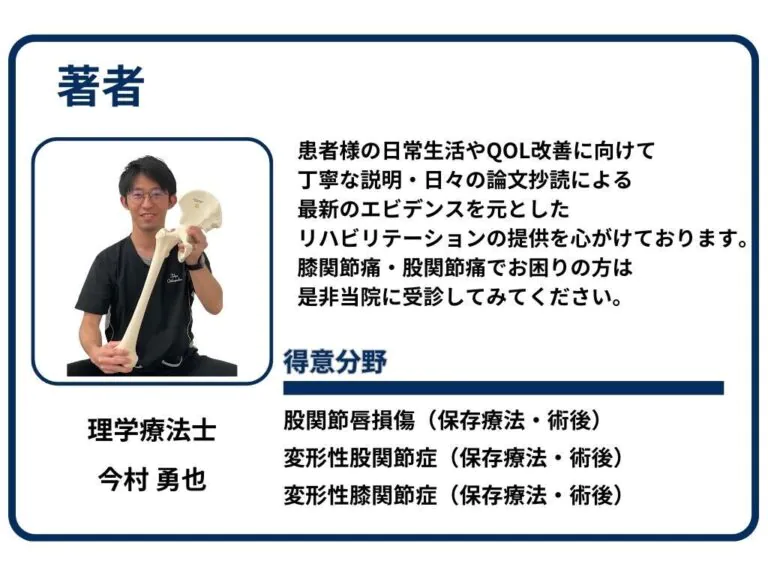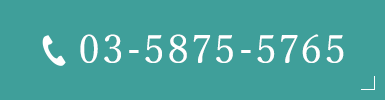変形性股関節症と骨粗鬆症の関連性とは?
今回のkey point
| 変形性関節症の患者では骨密度が高く、骨粗鬆症になりにくい |
| 骨粗鬆症は人工股関節周囲骨折のリスク要因となる |
変形性股関節症と骨粗鬆症の関連性とは?
日本人の高齢者に多い変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)と骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、一見別々の病気に思えます。しかし近年、これら二つの疾患の間に何らかの関連性があるのではないかと注目されています。本記事では、変形性股関節症と骨粗鬆症それぞれの基礎知識や原因、そして両者の関連性について解説します。また、骨粗鬆症が人工股関節置換術後の合併症リスク(インプラント周囲骨折など)に与える影響や、日常生活で気をつけたい予防のポイントについてもお伝えします。
1. 変形性股関節症と骨粗鬆症の基礎知識
変形性股関節症とは、股関節が長年の酷使や加齢などにより軟骨がすり減って変形し、痛みや可動域の制限を引き起こす病気です。関節痛、腫れ、関節の変形などの症状が現れます。進行すると歩行や立ち座りに支障をきたします。
以下に変形性股関節症の主なリスク要因を挙げます。
-
加齢(年をとるほど発症しやすい)
-
性別(女性に多い傾向があります)
-
股関節への過度な負荷(長年の重労働やスポーツ、肥満などによる関節への負担)
-
先天的要因(先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全など、股関節の形態異常)
-
遺伝的素因や肥満(遺伝要因、そして肥満は関節に負担をかけリスクを高めます)
一方、骨粗鬆症とは、骨の強度を保つカルシウムなどのミネラルが減少し、骨密度(骨組織の密度)が低下して骨がスカスカの状態になる病気です。骨の内部構造が脆くなることで骨折しやすくなり、とくに高齢女性で多く見られます。自覚症状が乏しく、進行すると背骨の圧迫骨折や大腿骨頸部(太ももの付け根)の骨折など重篤な障害を引き起こします。
主なリスク要因としては次のようなものがあります。
-
加齢・閉経(加齢とともに骨量が減り、閉経後の女性は女性ホルモンであるエストロゲンが低下で急激に進行)
-
性別(男性より女性に多い)
-
生活習慣(カルシウムやビタミンD不足、喫煙・過度の飲酒、運動不足)
-
体格(やせ型の人は骨量が少なくリスクが高い)
-
薬剤の影響や他疾患(副腎皮質ステロイドの長期使用や甲状腺機能亢進症など)
骨粗鬆症になると骨折リスクが高まるのは明らかですが、興味深いことに、変形性関節症との関連については昔から議論があります。例えば、変形性関節症の患者では骨密度が高く、骨粗鬆症になりにくいということが指摘されてきました。実際に、骨密度が高い人ほど変形性関節症のリスクが高まる傾向が報告されています。これは変形性関節症になる人の骨は局所的に硬く強くなるため、骨粗鬆症とは反対の性質を示すからです。
2. 両疾患の関連性に関する最新知見
変形性関節症と骨粗鬆症の関連性については、研究結果が一貫しておらず、現在も議論が続いています。高齢者に共通する二大疾患であるため、「たまたま両方併せ持つ人が多いだけでは?」という見方もありますが、最近では、それ以上に複雑な相互作用が示唆されています。
以下に最新の知見をいくつか紹介します。
-
骨粗鬆症は関節症になりにくい?:
遺伝的に骨粗鬆症になりやすい人ほど、将来的に変形性関節症を発症しにくい可能性が示されました。これは「骨粗鬆症があると変形性関節症の発生率が下がる」と結論づけています。 -
骨粗鬆症と関節症は併存しうる?:
一方で、変形性関節症の女性は骨粗鬆症を合併する率がやや高いことが示されました。特に肥満傾向にある人や喫煙歴のある人ではその関連が強く、変形性関節症でない人に比べて骨粗鬆症のリスクが約1.1〜1.2倍とわずかに上昇していきます。この増加は大きな差ではないものの、有意な関連性として報告されています。研究者らは「変形性関節症と骨粗鬆症の関連は一方向ではなく、肥満や生活習慣など第三の要因も絡んだ複雑なものだ」と指摘しており、今後さらに詳細な検証が必要とされています。 -
メカニズムの仮説:
変形性関節症と骨粗鬆症の関連を説明する仮説としては、いくつかのメカニズムが提案されています。例えば、変形性関節症では軟骨がすり減る際に骨への機械的負荷が増えて骨密度が局所的に高くなること、骨粗鬆症では骨微小構造の変化や炎症性物質の影響で軟骨の代謝に影響を及ぼす可能性などがあります。現在のところ結論は出ていませんが、「高齢」「遺伝素因」など共通のリスク因子を持つこともあり、両疾患は互いに無関係とは言い切れません。
3. 骨粗鬆症が人工股関節置換後の合併症リスクに与える影響
変形性股関節症が進行すると、痛みで歩行が困難になったり日常生活に支障が出たりするため、人工股関節置換術が検討されます。
人工股関節置換術自体は多くの患者さんにとって有効な治療法ですが、術後に注意すべき合併症の一つに人工関節周囲の骨折(周囲骨折)があります。骨粗鬆症の有無は、この周囲骨折のリスクに大きく影響します。
実際、近年では骨粗鬆症は人工股関節周囲骨折のリスク要因であることが明らかになりました。骨粗鬆症の患者では、人工股関節手術後にわずかな外力が加わっただけでも人工股関節周囲の骨が折れてしまうリスクが高まります。骨粗鬆症を持つ患者の人工股関節周囲骨折のリスクは骨密度が正常な患者の約2倍にのぼったとの報告があります。骨が脆いと人工股関節を骨に固定する力に耐えきれず、骨折だけでなく人工股関節のゆるみを引き起こす原因にもなります。人工股関節は骨にしっかりと圧入・固定されることで初めて安定しますが、骨粗鬆症ではその固定力が十分得られず、長期的に見て緩みやすくなるのです。
では、骨粗鬆症のある人が人工股関節手術を受ける場合、どうすればリスクを下げられるのでしょうか?
一つの有効策は骨粗鬆症そのものの治療です。例えば、骨粗鬆症の治療薬を服用することで、人工股関節置換後の骨の減少を抑え、周囲骨折の発生を予防できる可能性があります。術前に骨粗鬆症が疑われる場合は骨密度検査を行い、必要に応じて骨粗鬆症治療(内服薬や注射薬、カルシウム・ビタミンD補給など)を開始することが推奨されます。同時に、術後も適度なリハビリ運動で骨と筋肉を強化しつつ、主治医の指示に従って骨密度のモニタリングを続けると安心です。
4. 予防や日常生活で気をつけるポイント
変形性股関節症と骨粗鬆症、双方の予防には生活習慣の改善が重要な鍵となります。変形性関節症患者に対しては骨粗鬆症を予防・治療して骨の健康を維持すること、骨粗鬆症患者に対しては関節に負担をかけないよう配慮して関節の健康を守ることが大切だとされています。
以下、日常生活で気をつけたい具体的なポイントをリストアップします。
-
適度な運動習慣:
骨と筋肉を強くする運動は両疾患の予防に有効です。運動は骨に適度な刺激を与えて骨密度を保つほか、関節周囲の筋肉を鍛えて関節への負担を軽減します。ただし激しいジャンプや過度の荷重を伴う運動は関節を痛める恐れがあるため避け、痛みがあるときは無理しないことが肝心です。 -
食事で骨を強化:
バランスの良い食事を心がけ、骨の材料となるカルシウムやビタミンD、タンパク質を十分に摂取しましょう。 -
体重コントロール:
適正体重の維持も重要です。肥満傾向の方は減量により股関節への荷重を減らすことで変形性関節症の予防・症状緩和につながります。一方で過度の痩せ型は骨量低下を招き骨粗鬆症のリスクを高めます。 -
生活習慣の見直し:
喫煙や過度の飲酒は骨の健康に悪影響を及ぼします。禁煙は骨密度低下の抑制につながり、またアルコールは適量に留めましょう。睡眠不足や運動不足も体の回復力を下げますので、規則正しい生活リズムを整えることも大切です。 -
転倒予防と住環境の工夫:
骨粗鬆症の方にとって、転倒予防は骨折予防にも繋がります。家の中の段差をなくす、滑りにくい靴を履く、夜間照明を設置するなど環境を整備しましょう。万一転んでも大腿骨や股関節を直撃しないよう、手すりの活用や杖の使用も検討してください。 -
定期的な検診と早期対応:
骨密度検査や関節の状態チェックを定期的に受けることで、骨粗鬆症や変形性関節症の早期発見・早期対策が可能です。特に閉経前後の女性や、中高年で関節痛が出始めた方は、是非当院への受診をお勧めいたします。必要に応じて骨粗鬆症の薬物療法や変形性関節症の進行を抑えるリハビリ指導を受けることができます。
おわりに
変形性股関節症と骨粗鬆症は、高齢化社会において誰もが直面し得る身近な病気です。一見関係のないように思える二つの病気ですが、近年の研究から複雑な関連性が示唆されており、双方に適切に対処することが健康寿命を延ばすカギとなります。変形性股関節症の痛みで運動不足になると骨粗鬆症が進行しやすくなり、骨粗鬆症で骨が脆くなると関節手術のリスクが上がる。このように悪循環に陥らないよう、骨と関節の両面から予防策を講じることが大切です。
参考文献
・Lin L, Luo P, Yang M, Wang J, Hou W, Xu P. Causal relationship between osteoporosis and osteoarthritis: A two-sample Mendelian randomized study. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Oct 21;13:1011246.
・Huang K, Cai H. The interplay between osteoarthritis and osteoporosis: Mechanisms, implications, and treatment considerations - A narrative review. Exp Gerontol. 2024 Nov;197:112614.
・Fang Z, Zhao J, Zhang Y, Hua X, Li J, Zhang X. Relationship Between Osteoarthritis and Postmenopausal Osteoporosis: An Analysis Based on the National Health and Nutrition Examination Survey. Cureus. 2024 Oct 17;16(10):e71734.
・Ding X, Liu B, Huo J, Liu S, Wu T, Ma W, Li M, Han Y. Risk factors affecting the incidence of postoperative periprosthetic femoral fracture in primary hip arthroplasty patients: a retrospective study. Am J Transl Res. 2023 Feb 15;15(2):1374-1385.