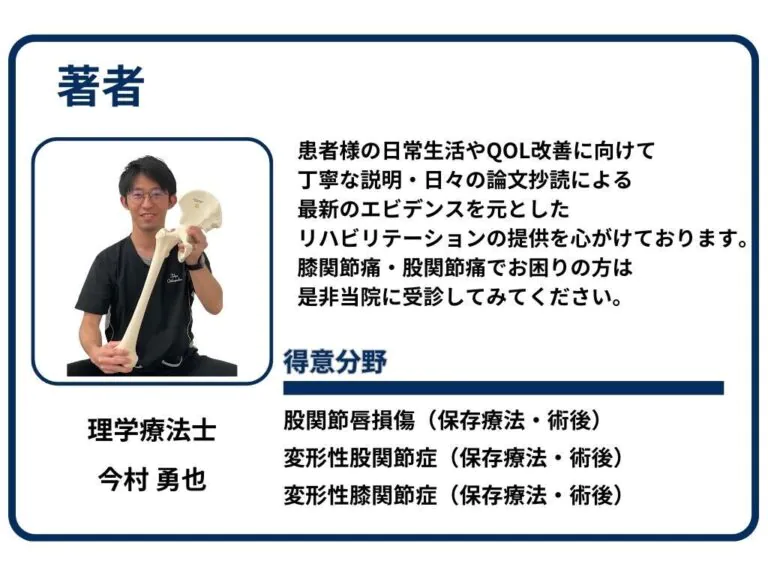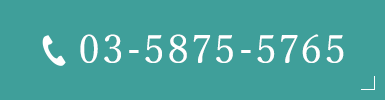変形性膝関節症の画像診断:X線とMRIの見方と注意点
今回のkey point
| レントゲン検査では関節の隙間や骨のトゲなどを評価する |
| レントゲン検査の重症度分類としてKellgren-Lawrence分類というものを用いる |
| MRIではレントゲン検査では映らない半月板や靭帯や骨の内部の状態などを検査する |
変形性膝関節症の画像診断:X線とMRIの見方と注意点
変形性膝関節症は、膝関節のクッションである軟骨がすり減り、関節の骨の縁にトゲ状の骨棘(こつきょく)ができて痛みや変形を引き起こす疾患です。中高年以降の特に女性に多く、進行すると膝の変形や強い痛みで日常生活に支障をきたすこともあります。その診断や進行度の評価には画像検査が重要です。
本記事では、膝のX線(レントゲン)検査とMRI検査に焦点を当て、それぞれの特徴や役割、画像からわかるポイント、検査を受ける際の流れと注意点などをわかりやすく解説します。
X線検査とMRI検査の違いと役割
X線検査(レントゲン)は変形性膝関節症の診断でまず行われる基本的な画像検査です。X線は骨をはっきり映し出すことができ、膝関節の骨の形や配置、関節の隙間の様子を見るのに適しています。一方で軟骨や靭帯、半月板といった骨以外の軟部組織は映らないため、軟骨の減り具合そのものは直接はわかりません。関節の隙間の広さから軟骨の厚みを間接的に推測するのがX線検査の特徴です。
MRI検査は磁石の力で体内の詳細な断面画像を得る検査で、軟骨や靭帯、半月板など軟部組織の状態まで詳しく調べることができます。レントゲンでは見えない軟骨のすり減りや損傷、半月板の損傷、膝に溜まった水(関節液)や骨の中の炎症(骨挫傷・骨髄浮腫など)もMRIでは確認が可能です。そのため、レントゲンに加えてMRIを行うことでより正確な診断や評価ができ、治療方針の決定にも有用です。特にX線画像で初期で見落としがちな変化もMRIなら捉えられることが多く、早期発見・早期治療に役立ちます。
X線画像でわかること:どんな変化が映る?
レントゲン画像から読み取れる主なポイントには以下のようなものがあります。
-
関節の隙間の狭さ(関節裂隙狭小化):
骨と骨の間の空間の広さです。軟骨がすり減ると隙間が狭くなり、進行度を示す重要なサインになります。例えば膝の内側の隙間が狭ければ、内側の軟骨が減っていることを意味します。立った状態で撮影したX線では体重がかかる分、隙間の減少がよりはっきりわかります(※横になって撮影すると隙間が広がり実際より軽く見えることがあるため、立った状態での撮影が推奨されます)。 -
骨棘(こっきょく):
関節の周りにできる骨のトゲ状の突起です。軟骨が減って骨同士が当たり不安定になると、生体の防御反応で余分な骨が形成されます。X線では白く突出した影として現れ、進行した変形性関節症の特徴です。骨棘は関節の縁に「引っかかり」や痛みを生むことがありますが、体を安定させようとする適応現象でもあります。 -
骨の硬化と嚢胞(のうほう)形成:
軟骨下骨(軟骨の下の骨)が圧力にさらされると硬く密になり、X線で通常より白く濃く映ります(骨硬化)。進行すると骨の中に嚢胞(骨嚢胞)と呼ばれる小さな空洞や穴ができ、黒い影として見えることもあります。 -
関節の変形とアライメントの乱れ:
軟骨の偏った消耗により、O脚(内側の隙間消失)やX脚(外側の隙間消失)といった脚の軸のずれが起こる場合があります。膝関節では内側の軟骨が傷みやすく、典型的には内側の関節隙が狭くなりO脚変形が進むことが多いです。また膝のお皿(膝蓋骨)と大腿骨の間の関節(膝蓋大腿関節)の隙間が狭くなる場合もあり、膝蓋骨のずれや変形もX線で確認できます。
レントゲン所見の重症度評価には、Kellgren-Lawrence(KL)分類と呼ばれる国際的指標が用いられています。この分類ではX線画像上の関節隙の狭小化の程度と骨棘の有無・大きさに基づき、0~4の5段階で進行度を評価します。
一般的にグレード2以上で変形性膝関節症と診断され、数字が大きいほど重度です。例えばグレード4では隙間がほとんど無く骨と骨が接触しかけ、骨棘も大きく形成された末期的状態を指します。レントゲン画像を見ることで自分の膝がどの程度進行しているか把握できますが、注意点としてレントゲン上の変化の大きさと痛みの強さは必ずしも比例しないことが挙げられます。
MRI画像でわかること:何がどこまで見える?
MRIではレントゲンでは写らない軟部組織や骨内部の変化まで観察できます。変形性膝関節症でMRIから得られる主な情報を挙げます。
-
軟骨の状態:
関節軟骨そのものの厚みや欠損具合がわかります。MRI画像では軟骨は白っぽく写り、摩耗している部分は薄くなったり途切れたりします。例えば「内側の軟骨がすり減って骨が露出している」「軟骨下骨がむき出しになっている」といった所見が確認できます。軟骨の欠損は進行度と関係し、早期発見できれば進行を食い止める治療につなげることができます。 -
半月板や靭帯の損傷:
膝関節のクッションである半月板の断裂や変性、膝の安定性を保つ靭帯(前十字靭帯など)の断裂もMRIで鮮明に写ります。変形性膝関節症では加齢とともに半月板にもダメージが蓄積し、実は症状がなくても高齢者では半月板損傷がよく見つかります。70歳代男性では50%以上に半月板断裂がみられるとの報告もあります。
半月板の後根部(奥の付け根)の断裂は膝の荷重バランスを崩し、軟骨の摩耗を一気に進行させる要因になることもわかってきました。MRIで半月板や靭帯損傷の有無を確認することは、手術が必要か判断する材料にもなります。
-
骨髄の異常(骨挫傷・骨髄浮腫):
レントゲンでは見えない骨の中の変化もMRIなら検出できます。骨の中に水分(浮腫)が溜まっている状態や微細な損傷(骨挫傷)は、MRIで骨内部が白く映る所見として現れます。これは骨髄浮腫とも呼ばれ、骨にかかる過度のストレスや微小骨折による反応で、痛みの原因となりうるものです。
X線上は軽度でもMRIで骨髄浮腫がある膝は痛みが強く出る傾向が報告されており、痛みの原因解明や将来の軟骨損傷リスク評価に役立ちます。
-
関節液の貯留や滑膜の炎症:
膝に水が溜まる(関節水腫)状態や、関節に栄養を供給して関節の周りを包む(関節包)の内側を覆う滑膜(かつまく)の炎症による肥厚もMRIで確認できます。炎症があるとMRIで造影をした際に滑膜が強く写り、これにより痛みや腫れの程度を評価します。滑膜炎は痛みと病気の進行に関与すると考えられており、MRI所見から痛みの原因が骨か軟骨か滑膜かを推測する助けになります。 -
その他の合併所見:
変形性膝関節症とは別に、膝関節周囲の腫瘍や嚢胞(例えばベーカー嚢腫という膝裏の嚢胞)などが痛みや腫れの原因になっている場合もあります。MRIはこうした他の病変を発見・鑑別する上でも有用です。
画像を読むときのポイントと注意
レントゲンやMRIの画像を患者さんが直接見る機会もあるかもしれません。そんなときに知っておくと理解が深まるポイントや、誤解しないための注意点を紹介します。
-
関節の隙間=軟骨の厚み:
繰り返しになりますが、レントゲン画像では黒い関節の隙間部分が軟骨に相当します。医師は「ここの隙間が減っていますね」と説明することで「軟骨が薄くなっています」という意味を伝えています。軟骨自体は見えないため、この隙間の幅=クッションの厚さと覚えておくとよいでしょう。 -
骨棘=骨のトゲ・引っかかり:
レントゲンで見られる骨棘は文字通り骨のトゲですが、専門用語で言われると難しいです。医師によっては「骨の縁にトゲができています」などといった比喩で説明してくれることもあります。骨棘そのものは痛みの原因になることもありますが、上述のように関節を安定させようとする体の反応でもあります。 -
画像所見と痛みのズレ:
画像で重度だからといって必ず強い痛みがあるわけではなく、逆に画像で軽度でも痛みが強い人もいます。例えばレントゲンで軟骨がほとんど無く骨同士が当たっていても、意外と痛みなく歩ける方もいますし、レントゲン上は軽い変形でも激痛で歩けない方もいます。この症状と画像所見の不一致は珍しくなく、痛みには軟骨のすり減り以外にも筋肉の状態や炎症の有無、骨の中の変化など複数の要因が関与するためです。医師は画像と患者さんの症状の両方を総合して診断・治療方針を決めます。「レントゲンでひどいと言われた=必ず手術しないと歩けなくなる」という訳ではありませんので、不安になりすぎず主治医とよく相談しましょう。 -
初期でも見逃さない:
変形性膝関節症の初期段階では、レントゲンにはほとんど異常が映らないこともあります。例えばKL分類でグレード0(正常)と判断された人でも、MRI検査をすると約9割もの人に実は骨棘や軟骨の変性、骨髄の異常(骨挫傷や浮腫など)が見つかったという報告があります。これはレントゲンだけでは初期変化を捉えにくいことを示しており、痛みがあるのにレントゲンで「異常なし」と言われても安心しきれない面があります。症状が続く場合は必要に応じてMRIや超音波検査などで詳しく調べることも検討されます。
まとめ
膝の痛みでお悩みの方に向けて、変形性膝関節症の画像診断(X線・MRI)のポイントを解説しました。X線検査はまず行われる基本の検査で、骨の変形度合いや関節の隙間(軟骨の厚み)を評価できます。進行度はKellgren-Lawrence分類などで段階付けされますが、画像所見と痛みが必ずしも一致しない点には注意が必要です。
MRI検査は軟骨や半月板など軟部組織の状態や骨内部の異常まで詳細にわかる検査で、レントゲンでは見えない初期の変化や痛みの原因を探るのに有用です。
画像を見る際のポイントとして、関節の隙間=軟骨の厚み、骨棘=骨のトゲといった図解を頭に入れておくと理解しやすくなります。
参考文献
・Piccolo CL, Mallio CA, Vaccarino F, Grasso RF, Zobel BB. Imaging of knee osteoarthritis: a review of multimodal diagnostic approach. Quant Imaging Med Surg. 2023 Nov 1;13(11):7582-7595.