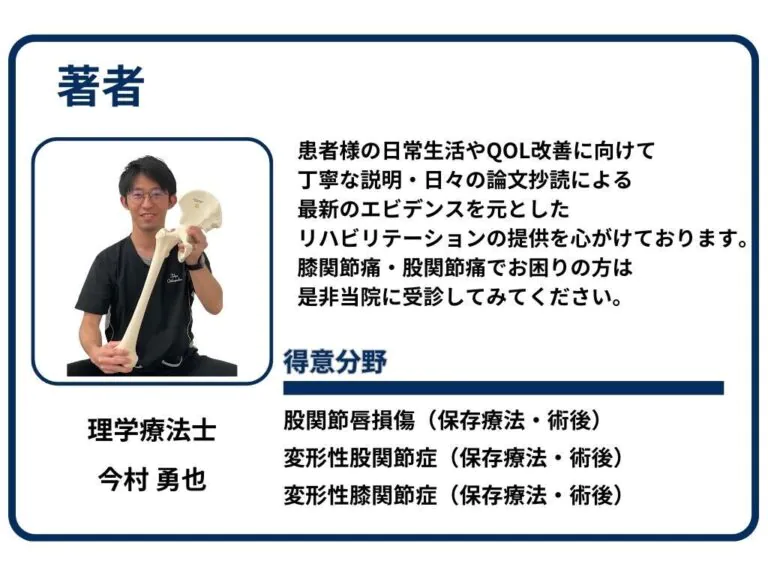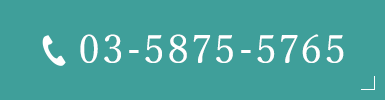女性ホルモン(エストロゲン)と変形性膝関節症の発症
今回のkey point
| エストロゲンには膝関節の軟骨を守る保護作用がある |
| 閉経後にエストロゲンの分泌が低下する |
女性ホルモン(エストロゲン)と変形性膝関節症の発症
40代以降の女性に多い膝の痛みとして代表的な原因が「変形性膝関節症」です。近年、変形性膝関節症と女性ホルモン(特にエストロゲン)の関係が注目されています。この記事では、変形性膝関節症の症状がなぜ女性に多いのかをエストロゲンの役割に着目して説明していきます。また、閉経前後のホルモンバランスの変化が関節に与える影響や、エストロゲンの持つ軟骨保護作用、さらに中年期以降の女性で発症リスクが高まる背景についても分かりやすく説明していきます。
変形性膝関節症とはどんな病気?
変形性膝関節症とは、主に加齢によって膝関節の軟骨(骨と骨の間のクッション)がすり減り、歩行時などに膝の痛みが生じる病気です。進行すると関節の変形(いわゆるO脚化など)や腫れが起こり、膝が十分に曲げ伸ばしできなくなることもあります。軟骨は一度すり減ると自然には元に戻らないため、加齢と長年の負担の積み重ねで少しずつ関節のダメージが蓄積し、症状が現れます。
この病気は高齢者に多く見られますが、特に女性に多いことが知られています。変形性膝関節症の患者数は女性が男性の約4倍にも上るとの報告があります。
なぜ女性に多いのでしょうか?その背景には、女性特有のホルモンバランスの変化が大きく関与しています。
女性に多い理由:エストロゲンの関与
女性に変形性膝関節症が多い理由の一つに、エストロゲン(女性ホルモン)の減少があります。男性も年齢とともに性ホルモン(テストステロンなど)が減少しますが、女性は閉経を境にエストロゲンの分泌量が急激に低下します。エストロゲンは骨や関節軟骨、筋肉の健康を保つ重要な役割を担っているホルモンです。そのため、閉経後にエストロゲンが減少すると膝の軟骨が保護しにくくなり、変形性膝関節症のリスクが高まると考えられています。
実際に、閉経後の女性で変形性膝関節症が増えることや、関節の軟骨細胞にエストロゲンの受け取り口が存在することが分かっており、エストロゲンの低下と変形性膝関節症には密接な関連があると指摘されています。これらのことから、エストロゲンには膝関節の軟骨を守る保護作用があると考えられています。
もちろん女性に変形性膝関節症が多い理由はホルモンだけではありません。平均的に女性は男性より筋肉量が少なく、膝を支える筋力が弱めです。その結果、関節への負担が大きくなりやすく軟骨がすり減りやすいことも一因とされています。しかし、中年期以降の女性で発症が増える要因は、急激なエストロゲン低下による軟骨への影響も考えられます。
閉経前後のホルモン変化が軟骨・関節に与える影響
女性は更年期(閉経の前後)にホルモンバランスが大きく変化します。エストロゲンの分泌量は閉経に向かって乱高下し、その後ほとんど分泌されなくなります。この閉経前後のエストロゲン低下は、膝の軟骨や関節にさまざまな影響を及ぼします。
エストロゲンは軟骨の健康維持に関与していますが、具体的には軟骨の主要成分であるコラーゲンやプロテオグリカンという物質の産生を助けています。ところが更年期にエストロゲンが減少すると、軟骨の新陳代謝が低下し、軟骨が作られにくくなるためすり減りやすくなります。その結果、関節のクッションが薄くなり、動くと痛みやこわばりが生じやすくなります。
また、エストロゲン自体に炎症を抑えて痛みを和らげる作用があるため、閉経でエストロゲンが少なくなると関節の痛みを感じやすくなることも報告されています。
要するに、閉経を境に女性の関節はホルモンによる保護を失うことになり、今までエストロゲンに守られていた軟骨が傷みやすくなるのです。
中年期以降の女性で発症リスクが高まる背景
変形性膝関節症は特に中年以降の女性で増加します。実際、年齢別に見ると40歳を過ぎた頃から変形性膝関節症の発症数が顕著に伸び始めることが知られています。
中年期以降の女性でリスクが高まるのは、以下のような複数の要因が重なるためです。
-
加齢の影響:
年齢とともに軟骨の弾力や再生力が低下し、長年の酷使で少しずつ擦り減っていきます。誰にでも起こる自然な老化現象ですが、中年期以降はその蓄積が表面化しやすくなります。 -
ホルモンバランスの変化:
閉経前後でエストロゲンが急減し軟骨への保護作用が弱まります。これは中年女性特有のリスク要因で、加齢による軟骨摩耗に拍車をかける形になります。 -
筋力の低下:
加齢や運動不足により太ももの前側など膝を支える筋肉が衰えると、膝関節にかかる負担が増え軟骨が磨耗しやすくなります。特に女性は男性より筋肉量が少ない傾向があり、中年期以降は筋力低下が進みやすいことから膝への負荷が大きくなります。 -
体重の増加:
更年期以降は代謝の変化などで体重が増えやすく、肥満傾向になると膝にかかる荷重が大きくなります。体重そのものが増えていなくても、筋肉が落ちて脂肪が増えるだけで膝への負荷は増大します。こうした体重・体質の変化も膝軟骨をすり減らす要因です。 -
その他の要因:
遺伝的な体質や、日常生活や仕事で膝に慢性的な負担をかける動作(重い物を運ぶ、正座の習慣など)、O脚など脚のアラインメント異常も発症リスクを高めるとされています。
以上のように、中年期以降の女性は年齢的な変化(軟骨の老化や筋力低下)にホルモン環境の変化(エストロゲン低下)が重なり、さらに生活習慣や体型の変化も影響して、膝関節症を発症しやすい状況になります。
まとめ
変形性膝関節症は膝の軟骨がすり減ることで起こる慢性的な関節の病気で、女性に特に多く見られます。その大きな原因の一つが女性ホルモン(エストロゲン)の減少です。エストロゲンは骨や軟骨を守る大切なホルモンで、閉経に伴う急激なエストロゲン低下が軟骨の変性を進め、変形性膝関節症のリスクを高めます。更年期前後のホルモンバランスの変化によって関節痛が起こりやすくなるのも、エストロゲンが担っていた軟骨保護作用や抗炎症作用が弱まるためと考えられます。
とはいえ、変形性膝関節症の発症には加齢や筋力低下・体重増加といった生活習慣・体質的な要因も深く関わっています。中年期以降の女性はこうした複数の要因が重なるため注意が必要です。日頃から適度な運動で太ももの筋肉を鍛えたり、体重管理を行ったりすることで膝への負担を減らし、軟骨のすり減りを予防することが大切です。膝の痛みを感じ始めたら無理をせず、早めに整形外科などで相談して適切な対策をとるようにしましょう。女性ホルモンの変化を正しく理解し、上手に付き合っていくことで、いつまでもアクティブな膝と付き合っていけるはずです。
参考文献
・Roman-Blas JA, Castañeda S, Largo R, Herrero-Beaumont G. Osteoarthritis associated with estrogen deficiency. Arthritis Res Ther. 2009;11(5):241.