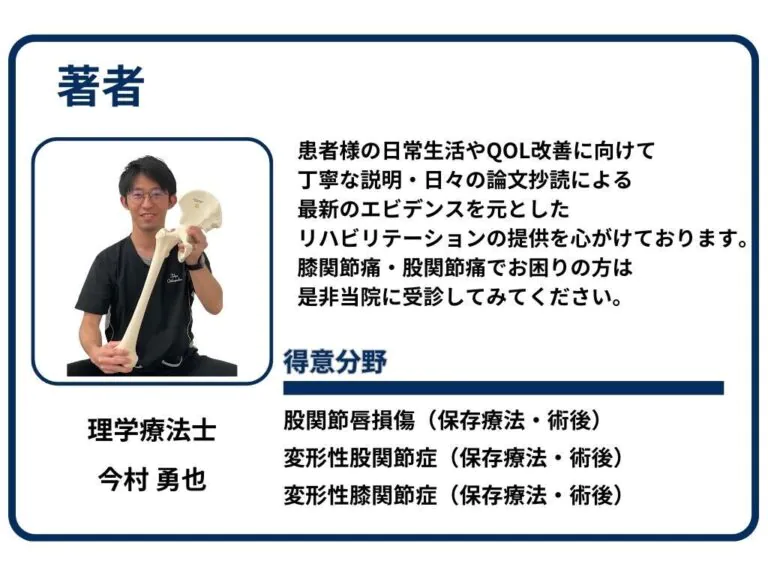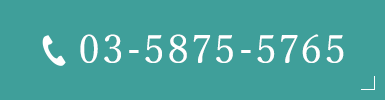膝から鳴るポキポキ・ゴリゴリ音の原因と対処法
今回のkey point
| 膝のポキっとする音は基本的には病的な音ではない |
| 膝のゴリゴリする音やパキッとする音は膝の病的な原因が隠れている可能性がある |
膝から鳴るポキポキ・ゴリゴリ音の原因と対処法
膝を曲げ伸ばしするたびに「ポキッ」「ゴリゴリ」と音が鳴ると不安になりますよね。実は高齢者の約6割が膝の音を経験すると報告されており、音自体は珍しい現象ではありません。ただし、中には関節の病気のサインとなる場合もあります。
本記事では、膝から聞こえるクリック音(ポキポキ音)とゴリゴリ音の違いや主な原因、放置してよいケースと注意すべきケース、関連する代表的な疾患、そして対処法・予防法について、わかりやすく解説します。
膝が鳴る音の正体とは?(クリック音とゴリゴリ音の違い)
膝を曲げ伸ばししたときに鳴る音には大きく分けて2種類あります。
一つは「クリック音」と呼ばれるポキポキ・パキパキと乾いた単発の音で、もう一つは「ゴリゴリ音」と表現されるミシミシ・ジャリジャリとした連続的な摩擦音です。
それぞれ原因が異なり、危険性も異なります。
-
クリック音(ポキポキ音) –
指の関節を鳴らす時と同じように、関節液内の小さな気泡が弾けることで生じる音です。急に関節を動かすと圧力変化で関節液にできた気泡が破裂し、「ポキッ」という乾いた音が鳴ります。膝だけでなく指や首などでも起こる生理現象で、痛みを伴わない場合は基本的に心配いりません。一度鳴ると同じ箇所ではしばらく鳴らないのも特徴です。 -
ゴリゴリ音(ミシミシ音) –
軟骨や半月板の摩耗などで関節の表面が粗くなり、動かすたびに発生する摩擦音です。変形性膝関節症などにより膝の軟骨がすり減ると、関節の動きが滑らかでなくなり「ギシギシ」「ジャリジャリ」といった音が毎回の動作で聞こえることがあります。この音は関節内の異常を示すことが多く、痛みや違和感を伴う場合もあります。膝のお皿(膝蓋骨)周辺でゴリゴリ音がする場合、膝蓋軟骨軟化症(膝のお皿裏の軟骨損傷)などの可能性も指摘されています。
なお、膝を動かす際の「腱や靭帯の引っかかり」による音もあります。膝周辺の筋や靭帯が骨の出っ張りに引っかかって弾かれるとき、「パキッ」や「コリッ」という音が出ることがあり、これは特定の動きで繰り返し発生します(例:階段の昇降で毎回コリコリ音がする等)。
このタイプの音は引っかかり感を伴いますが、炎症がなければ痛みを伴わないことも多いです。靭帯や腱の引っかかりによる音は生理的な範囲で起こることもありますが、繰り返し頻繁に起こる場合は膝のアライメント(骨の位置関係)の乱れが原因になっている可能性があります。
まとめると、痛みのない単発のクリック音は気泡や腱の動きによる生理現象であることが多く、深刻な問題ではないのに対し、ゴリゴリと擦れる音や引っかかる感じを伴う音は関節の変性や損傷が原因の場合があり注意が必要です。
膝の音はどんな場合に要注意?
膝の音そのものは必ずしも異常ではありませんが、次のような場合は関節の病的な変化のサインかもしれません。
心当たりがあれば早めに整形外科を受診しましょう。
-
音と同時に痛みを感じる場合:
音が鳴る瞬間に膝に痛みが走る場合、関節内部に損傷がある可能性があります。痛みを伴う膝の音は病的な雑音であることが多く、放置せず専門医の診察を受けることが勧められます。特に強い痛み(目安として10段階中4以上の痛み)がある時は注意が必要です。 -
膝に腫れや熱感を伴う場合:
関節に炎症が起きているサインです。関節リウマチなどの炎症性疾患や半月板・靭帯損傷により関節液が増えて腫れるケースも考えられます。 -
膝が引っかかって動かなくなる(ロッキング)場合:
膝を曲げ伸ばしする途中で動きが止まるような「引っかかり」を感じる場合、半月板の断裂片や関節内の遊離体(関節ねずみ)が邪魔をしている可能性があります。ロッキングを伴う場合は緊急に整形外科で評価が必要です。 -
頻繁に音が鳴り、回数が増えてきている場合:
最初は時々だった音が1日のうちに何度も鳴るようになったり、月単位で徐々に頻度が増している場合は要注意です。変形性膝関節症の初期症状として、痛みが出る前に膝の違和感や音が増えてくることがあります。
上記の「危険サイン」がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。
逆に、痛みや腫れを伴わない軽いポキポキ音だけで他に症状がなければ、多くの場合それ自体は無害と考えられます。単発のクリック音のみで膝に痛みがなければ深刻に心配する必要はありません。
ただし、「最近音が大きくなってきた」「違和感が強く気になる」といった場合は早めに専門医に相談し、検査で原因を確認することをお勧めします。
膝の音に関連する代表的な疾患
膝から音が鳴る背景には、以下のような関節の疾患が隠れていることがあります。それぞれの特徴と膝の音との関係を解説します。
中高年に多い膝の病気で、長年の負担や加齢により膝関節の軟骨がすり減って変形してしまう疾患です。
日本では膝痛患者の8~9割が変形性膝関節症によるとも言われるほど一般的な病気です。
この疾患では初期の段階で膝を動かすと音が鳴る、違和感があるといった症状が現れることがあります。軟骨の表面が摩耗してざらつくため、膝を曲げ伸ばしする際に「ジャリジャリ」「ギシギシ」と擦れる音(粗造音)が生じるのです。実際、軟骨が50%以上欠損した患者の約78%に摩擦音(粗造音)が認められたという報告もあります。
変形性膝関節症が進行すると、一時的に音が感じられなくなることもあります。
軟骨がさらにすり減って関節液が増える中期には摩擦音が小さくなることがありますが、これは良くなったわけではありません。末期になると軟骨の下地の骨同士がぶつかり合い、再びゴリゴリという骨と骨が擦れる音が生じるようになります。
音が一時収まっても病変は進んでいるため、膝に違和感や音がある段階で適切な対策をすることが重要です。
半月板損傷(はんげつばんそんしょう):
半月板は膝関節内にある軟骨で、クッションの役割をしています。スポーツで膝をひねったり、加齢で脆くなった半月板に負荷がかかったりすると半月板が裂けて損傷することがあります。
半月板損傷では膝を動かしたときに「コリッ」というクリック音が生じることがよくあります。これは裂けた半月板の断片が関節にはさまったり引っかかったりするためで、音とともに膝の痛みや引っかかり感(膝がロックする感じ)を伴うのが特徴です。
損傷が進行すると膝に水(関節液)がたまったり、断裂片が完全に関節に挟まって激痛で動かせなくなるロッキング現象が起こることもあります。
半月板損傷を放置すると、膝のクッションが失われるため将来的に変形性膝関節症を招きやすくなります。
そのため、クリック音や引っかかりを伴う半月板損傷が疑われる場合は早期に治療し、必要に応じて断裂した半月板の縫合や部分切除などの処置を検討します。
日常的には大腿四頭筋(太ももの前側)を鍛えることで膝関節を安定させ、半月板への負担を軽減することが予防につながります。
関節リウマチ:
関節リウマチは自己免疫の異常によって関節に炎症が起こる病気です。主に手指の関節で知られますが、膝を含む全身の関節が影響を受けることがあります。
膝がリウマチに侵されると滑膜という関節内の組織が腫れて関節液が過剰に溜まり、膝が腫れて熱を帯びます。炎症が続くと軟骨や骨も破壊されていくため、初期の段階から膝の違和感や関節音(ミシミシというような音)を自覚することがあります。
関節リウマチの場合、朝のこわばり(起床時に関節が固まって動かしにくい)や左右両膝に症状が出る傾向など、他の疾患とは異なる特徴もあります。
放置すれば関節破壊が進み、膝の変形や強い痛みに繋がります。膝に限らず複数の関節で腫れと痛みがある場合は、早めにリウマチ専門医を受診して治療を開始することが大切です。
その他の原因となる疾患:
上記以外にも、膝の音に関与する疾患があります。
タナ障害(膝の滑膜ヒダ障害)では膝関節内の滑膜ヒダというひだ状の組織が炎症・肥厚し、膝の曲げ伸ばしで膝の内側にクリック音を生じることがあります。
また、膝蓋軟骨軟化症(しつがいなんこつなんかしょう)は若年者に多い膝のお皿の軟骨障害で、膝を動かすとゴリゴリと軋む音や膝前面の鈍い痛みが現れます。適切な治療とリハビリで改善しますが、放置すると慢性化することがあるため注意が必要です。
さらに、スポーツ選手にまれに起こる離断性骨軟骨炎では、膝関節内の骨軟骨の一部が剥がれて遊離体(関節ねずみ)となります。大きな骨軟骨片が関節内で遊離すると、膝の中で「ゴリッ」と音がすることがあります。この場合もしばしば激痛やロッキングを伴うため、早急な治療介入が行われます。
膝の音への対処法と予防策
痛みのない生理的な範囲の音であれば特別な治療は不要ですが、気になる場合や将来的な膝の健康のために次のような対処・予防策を取ると良いでしょう。
-
太ももの筋力トレーニング:
大腿四頭筋を中心に膝周りの筋肉を鍛えることで関節を安定させ、摩擦音の軽減や膝への負担減少につながります。例えば、椅子に座った状態で片脚ずつ膝を伸ばして5~10秒キープする運動や、軽いハーフスクワット(膝を45度程度曲げる)などは有効です。適度な筋力強化は粗造音を約22%減少させたとの報告もあります。 -
ストレッチと柔軟性の向上:
太ももの前後(ハムストリングスや大腿四頭筋)や膝周りの筋をストレッチして柔軟性を高めると、関節への不必要なストレスが減り音の改善につながります。特に膝の屈伸に関わるハムストリングスや腸脛靭帯のストレッチを日常的に行いましょう。 -
膝に負担をかける習慣を見直す:
深くしゃがみ込む正座の姿勢は膝軟骨に強い圧力をかけ、また腱の引っかかりの音も増やします。長時間の正座やひざまずいての家事などは控えめにし、どうしても必要な場合は合間に脚を伸ばして休憩しましょう。また、立ち上がる時にいつも片脚に体重をかける癖があると片側の軟骨が偏って摩耗しやすくなります。日常の姿勢や動作を見直し、膝にかかる負担を両脚均等にする工夫も予防になります。 -
適度な運動と体重管理:
関節を支える筋肉を落とさないよう適度に身体を動かすこと、そして肥満傾向の方は体重を適正化することも大切です。運動不足で筋力が低下すると関節の位置関係が安定せず音が鳴りやすくなるとの指摘があります。ウォーキングや軽いスクワットなどで筋力維持に努めましょう。一方、過体重は膝軟骨の消耗を早めますので、食事改善などで膝への荷重を減らすことが予防につながります。 -
無理に音を鳴らさない:
指をボキボキ鳴らすのと同様に、膝も意図的に強く鳴らすことは避けましょう。痛みなく偶発的に鳴る分には問題ありませんが、無理に鳴らすと滑膜を刺激して炎症を起こす可能性があります。自然に鳴ってしまう程度であれば構いませんが、「癖で頻繁に鳴らしてしまう」という方は控えるようにしてください。
以上の対策を講じても膝の音や違和感が改善しない場合や、前述の危険サインがある場合には専門医による評価を受けましょう。早期に対応することで関節の寿命を延ばし、将来的な深刻な障害を防ぐことができます。
まとめ
膝の音そのものは珍しいものではなく、痛みや腫れを伴わない場合は過度に心配する必要はありません。一方で、膝が発する音は私たちに関節の状態を知らせる大切なサインでもあります。音の種類(クリック音かゴリゴリ音か)や同時に起こる症状に注目することで、安心してよいケースか注意すべきケースかを判断する材料になります。もし赤信号となる症状(痛み・腫れ・引っかかり)がある場合は、できるだけ早く整形外科を受診することが「膝の寿命」を延ばす近道です。日頃から適度な運動とケアで膝を労わり、“膝の音”とうまく付き合っていきましょう。
参考文献
・Song, S, et al. (2018). Noise around the Knee. Clinics in orthopedic surgery, 10(1)
・Baker, K, et al(2001). The efficacy of home based progressive strength training in older adults with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. The Journal of rheumatology, 28(7), 1655–1665.