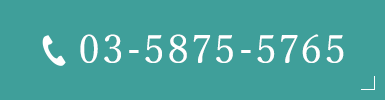膝痛・股関節痛の方へ——骨粗鬆症の検査が 大切な理由
膝痛・股関節痛の方へ——なぜ「骨粗鬆症の検査」が大切なのか
はじめまして。10月から当院に赴任した副院長の渡部(わたなべ)と申します。今後、不定期にはなりますがブログを更新していこうと思っています。
僕は膝・股関節に特化した診療を行っていますが、骨粗鬆症学会の認定医も持っています。
ひざや股関節が痛くて来院され、理学療法(リハビリ)、投薬、手術などの治療中や、治療を経て元気になった方が、治療とは関係なく骨粗鬆症に起因して発生する骨折やインプラントの不具合などに悩むことがないように手助けをさせていただきたいと思っています。そんな僕からひざ痛、股関節痛の方へ向けて骨粗鬆症検査の大切さについてお話をさせていただきます。
膝関節や股関節の痛みで受診される方の多くが、「軟骨や筋肉の問題であって、骨密度は関係ないのでは?」と考えがちです。ところが**骨粗鬆症(骨の脆さ)**は、①痛みの長期化、②転倒・骨折リスクの増大、③将来の治療(とくに人工関節手術)の安全性と成績、のいずれにも密接に関わります。早く見つけ、骨の状態を“見える化”してから治療計画を立てることが健康寿命の延伸(元気なままでいること)につながります。
骨粗鬆症が膝・股関節の痛みやその経過に影響する3つの理由
1)痛みをこじらせる土台要因
骨がもろいと荷重に耐える力が弱く、微小な損傷が起こりやすくなります。結果として痛みが慢性化し、日常動作のたびに症状がぶり返す悪循環に陥りがちです。
2)活動性の低下→さらなる骨・筋の弱化
痛みで動けない期間が延びるほど骨量・筋量が減少し、転倒・骨折リスクが上昇します。膝痛・股関節痛のリハビリ効果を最大化するには、**骨の強さ(骨密度)**を同時に整えることが欠かせません。
3)手術が必要になったときの安全性
この3番が特に大切になってきます。最終的に人工膝関節・人工股関節などの手術が必要になった際、インプラントの選択や初期固定の安定性は、骨の質にも影響を受けます。骨が脆いと術中・術後の周囲骨折リスクや固定性の低下リスクなどが生じます。
 術前から骨密度評価と適切な治療を行うことで手術の安全性と成績の向上が期待できます。
術前から骨密度評価と適切な治療を行うことで手術の安全性と成績の向上が期待できます。
骨粗鬆症・骨密度の検査で何がわかる?
DXA(デキサ)法は、腰椎と大腿骨近位部を測り、若年成人平均との比較値「Tスコア」で判定します。
-
Tスコア -1.0〜-2.5:骨量減少
-
Tスコア ≤ -2.5:骨粗鬆症
Tスコアが-2.5未満であれば、それだけで骨粗鬆症の診断となり、治療が必要です。
一方、Tスコアが1.0~-2.5の骨量減少であれば、他に脆弱性骨折(手首や肋骨などの骨折)を合併していたり、FRAX(年齢・体重・既往歴などを加味)というスコアリングでの骨折リスクの高さや、糖尿病やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の合併など、骨質不良を合併する場合は治療が必要となります。柔道で言うところの合わせ技一本というところでしょうか。
脊椎X線で隠れた圧迫骨折が確認されれば、骨密度が高くとも骨粗鬆症の診断となり、その治療適応となります。
どんな人が検査を受けるべき?(目安チェック)
-
65歳以上の女性
-
閉経後で危険因子あり(低体重、家族歴、喫煙、飲酒、ステロイド内服、リウマチなど)
-
脆弱性骨折の既往(つまずいただけで折れたなど)
-
身長の低下・姿勢の変化(圧迫骨折が疑われる)
- 糖尿病・COPDなど骨質低下のリスクとされる方。
-
人工関節手術を検討中、あるいは術後の骨折予防を強化したい方
上記に当てはまる方は、痛みの種類にかかわらず一度DXA(骨密度検査)を行うことを勧めます。男女ともに個別のリスク評価が重要です。
検査結果をどう治療に活かすか(実践ロードマップ)
1)運動療法の“負荷設計”
骨密度や転倒リスクに応じて、荷重量・頻度・進行スピードを最適化。膝関節・股関節の関節保護姿勢や**筋力強化(大臀筋・大腿四頭筋・中殿筋)**を段階的に実施します。
2)栄養と日常習慣
タンパク質、カルシウム、ビタミンDを十分に。日光曝露・屋外歩行、禁煙・節酒、適正体重の維持が基本です。
3)薬物療法の選択
上記のように骨折リスクが高い場合は、薬物治療の適応となります。薬の開始・切替・休薬は半年に1回のDXAと採血の骨代謝マーカー(TRACP-5B,P1-NP)で評価し、体内で「骨をつくる」、「骨をこわす」の働き(骨代謝といいます)がどのように動いているのかを半年に1回調べます。(このあたりの内容は後日また投稿できたらと思います)
4)転倒予防プログラム
バランス訓練、住環境の見直し(段差・照明・手すり)、履物のチェック等を組み合わせ、**“転ばない身体と環境”**を整えます。
5)手術を見据える場合
術前から骨粗鬆症の治療をしておくと、術中術後合併症(周囲骨折・ゆるみ)リスクの低下が期待できます。これは人工膝関節置換術・人工股関節置換術の双方で重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 検査は痛いですか?
A. DXAは低線量X線で5〜10分ほど。痛みはありません。
Q. 骨密度が低かったら、もう運動はできませんか?
A. いいえ。正しい負荷設計をすれば運動はむしろ有効です。筋力・バランス向上は転倒予防と痛み軽減に直結します。
Q. サプリだけで十分ですか?
A. 栄養は基盤ですが、運動・生活習慣・必要に応じた薬物療法を組み合わせてこそ効果が最大化します。
まとめ——“骨の状態”を知ることが、膝・股関節治療の近道
-
骨粗鬆症は痛みの慢性化・骨折リスク・手術成績に影響します。
-
骨密度検査(DXA)、および採血の骨代謝マーカー(TRACP-5B,P1-NP)で骨の現状と骨折リスクを見える化し、運動・栄養・薬を必要なだけ、必要な順で組み合わせます。
-
膝痛・股関節痛がある方、手術を検討している方、危険因子がある方は早めの検査をおすすめします。
骨粗鬆症の治療は歯磨きと一緒です。歯のインプラント治療をした後に歯磨きをしない方はいらっしゃらないと思いますが、同じように関節の治療前後で骨粗鬆症の治療を行うことが必要だと考えます。
当院では、骨密度DXA・関連採血・画像評価までを一貫して行い、結果にもとづく個別のリハビリと骨粗鬆症治療をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
膝・股関節痛でお困りの方はご予約ください。
参考文献
-
US Preventive Services Task Force. Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: Recommendation Statement. JAMA. 2018;319(24):2521–2531. doi:10.1001/jama.2018.7498
-
Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women—2019 update. Osteoporosis International. 2019;30(1):3–44. doi:10.1007/s00198-018-4704-5
- Watanabe N, Ogawa T, Takada R, Amano Y, Jinno T, Koga H, Yoshii T, Okawa A, Miyatake K. Association of osteoporosis and high serum homocysteine levels with intraoperative periprosthetic fracture during total hip arthroplasty: a propensity-score matching analysis. Arch Orthop Trauma Surg
. 2023 Dec;143(12):7219-7227. doi: 10.1007/s00402-023-04989-6.
渡部直人 専門分野 膝・股関節

日本整形外科学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、医学博士
ひざや股関節が痛くて来院され、理学療法(リハビリ)、投薬、手術などの治療中や、治療を経て元気になった方が、治療とは関係なく骨粗鬆症に起因して発生する骨折(椎体骨折、大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折など)やインプラントの不具合などに悩むことがないように手助けをさせていただきたいと思っています。