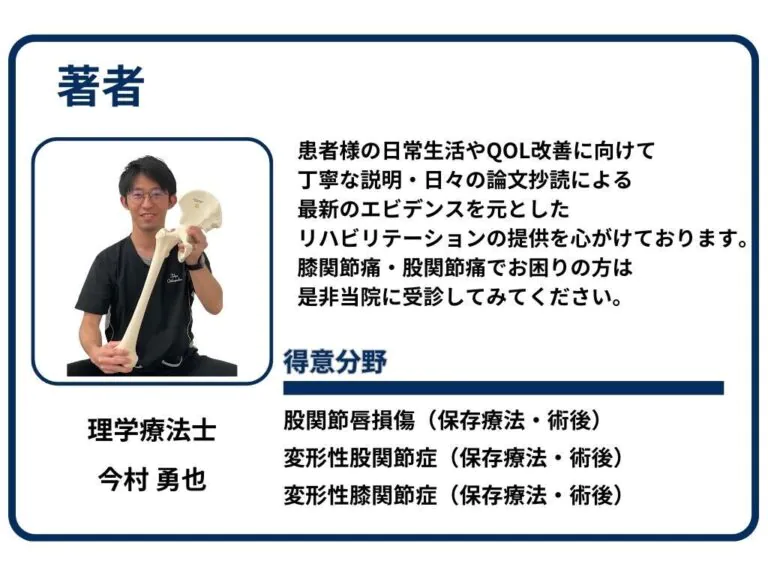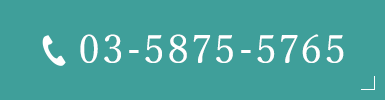臼蓋形成不全と股関節唇損傷の関連性
今回のkey point
| 臼蓋形成不全の8割に股関節唇損傷が存在する |
| 股関節唇損傷は変形性股関節症になりやすい |
股関節の「隠れた原因」かも?──臼蓋形成不全と股関節唇損傷について
みなさんは、股関節が痛いと感じたことはありませんか?
実はその痛み、「臼蓋形成不全」や「股関節唇損傷」という病態が関係しているかもしれません。
この記事では、最新の医学研究をもとに、臼蓋形成不全と股関節唇損傷のつながりについて、わかりやすくご紹介します。
臼蓋形成不全ってなに?
「臼蓋(きゅうがい)」とは、骨盤にある、太ももの骨の先端(大腿骨頭)を包み込む“受け皿”のような部分です。
普通はこの受け皿が深く、太ももの骨をしっかり支えています。
ところが、臼蓋形成不全があると、この受け皿が浅くて、骨の支えが弱くなってしまうのです。
その結果、股関節がぐらつきやすくなり、体重がかかるたびに、関節の中に負担やズレが生じるようになります。
股関節唇ってなに?
股関節の中には、「股関節唇」と呼ばれる小さなクッションのような組織があります。
この股関節唇があることで、関節がピタッと密着し、動きがなめらかになり、安定性も高まります。
ところが臼蓋形成不全があると、股関節唇に余計な力がかかり、傷ついてしまう(損傷する)ことがわかっています。
どのくらい関係しているの?
ある研究では、臼蓋形成不全がある人の約8割以上で、股関節唇に損傷が見つかることが報告されています。
つまり、臼蓋形成不全があると高い確率で股関節唇も傷つくということになります。
どんな症状が出るの?
股関節唇損傷は、こんな症状が出ることがあります。
-
股関節の前側(そけい部)が痛い
-
歩いたり階段を上ったりすると痛みが出る
-
足の付け根で「コリッ」「パキッ」と音がする
-
関節が引っかかるような違和感がある
ただし、臼蓋形成不全だけでも似たような症状が出ることがあり、股関節唇損傷だけを特別に感じ取るのは難しいとされています。
股関節唇損傷の診断方法とは?
股関節唇損傷はスポーツをされている方や、股関節に負担がかかる動作が多い方に比較的多くみられます。正確な診断には、問診・診察・画像検査を組み合わせた総合的な評価が必要です。
身体診察:FADIRテストがカギ
診察時には、FADIRテストという動作テストを行います。これは股関節を深く曲げて内側にひねる動作で、痛みが再現されるかを確認します。この検査で痛みが出た場合、股関節唇損傷がある可能性が高くなります。
画像検査:まずはX線、その後MRIへ
画像検査ではまずX線(レントゲン)を撮影し、臼蓋形成不全(股関節の受け皿の浅さ)や骨の変形の有無を確認します。ただし、X線では股関節唇自体は写らないため、さらに詳しい検査としてMRIが必要になります。
より精密な診断を行うためには、関節内に造影剤を注入して撮影するMR関節造影(MRA)が有効です。MRAでは、通常のMRIでは見逃されやすい微細な損傷も明瞭に描き出すことができます。
症状があるのに画像で分からない?そんな時は注射で診断
MRIで明確な異常が見られない場合でも、痛みや他の所見から股関節唇損傷が疑われることがあります。そんな時には、エコーで誘導しながら股関節内に局所麻酔を注射する検査を行うことがあります。注射後に痛みが一時的に消失すれば、痛みの原因が股関節内、すなわち股関節唇にある可能性が高くなります。
放っておくとどうなる?
股関節唇損傷によって、その周囲の関節の軟骨も痛みやすくなることがわかっています。
実際に調査では、
-
股関節唇損傷がある場所では、約6割に軟骨の損傷も確認。
-
股関節唇が正常な場所では、軟骨の損傷はわずか1割以下。
つまり、股関節唇損傷は、将来的な変形性股関節症のリスクにもつながるのです。
治療法:保存療法から手術まで
股関節唇損傷の治療は、まずは保存療法(手術を行わない治療)から始めるのが一般的です。股関節唇は自然に元通りになることはほとんどありませんが、痛みを抑え、股関節の機能を保つことを目指します。
保存療法では、まず安静を保ち、痛みの強い動作(深いしゃがみ込みや開脚など)を避けることが重要です。必要に応じて消炎鎮痛剤(NSAIDs)を使用し、股関節周囲の筋肉を整えるリハビリ(理学療法)を進めていきます。特に中殿筋や腸腰筋など、股関節を支える筋肉の強化や柔軟性の改善が、症状の軽減につながります。
しかし、数か月間の保存療法でも改善が見られない場合は、手術療法が選択肢となります。
中等度以上の臼蓋形成不全がある場合は注意が必要です。骨の受け皿が浅いままでは、股関節鏡手術で修復・縫合した股関節唇に再び負荷が集中し、再損傷のリスクが高まります。そのため、骨盤の骨を回転させて股関節を覆う角度を調整する手術(RAO:寛骨臼回転骨切り術)が必要になります。
この骨切り術は体への負担が大きく、入院やリハビリも長期になることがありますが、若年で関節の変性が進んでいない患者さんには、将来的な変形性股関節症への進行を防ぐ根本的な治療として有効です。
患者さんの年齢、臼蓋形成不全の程度、軟骨の状態などを総合的に評価し、最適な治療方針を立てることが大切です。
もし軟骨がすでにすり減ってしまい、骨同士がぶつかるような末期状態になっている場合には、人工股関節置換術が選択されることもあります。ただし人工関節には耐用年数があるため、可能であれば自分自身の関節を長く使い続けることが望ましいとされています。
まとめ
・臼蓋形成不全があると、股関節唇が傷つきやすい
・股関節唇損傷は、将来の軟骨損傷や変形性股関節症のリスクになる
・早期に診断して、適切な治療(ときには手術)を考えることが大切
おわりに
もし股関節の痛みや違和感が続く場合、
「年齢のせい」「運動不足かな」と思わずに、一度当院へ受診して相談してみることをおすすめします。
今なら、早めに対処すれば関節を守れる可能性も十分にあります。
あなたの未来の健康のために、早めの一歩を踏み出しましょう!
参考文献
-
Jayasekera N, Aprato A, Villar RN. Hip Arthroscopy in the Presence of Acetabular Dysplasia. Open Orthop J. 2015 May 29;9:185-7.
-
Nishii T, Tanaka H, Sugano N, Miki H, Takao M, Yoshikawa H. Disorders of acetabular labrum and articular cartilage in hip dysplasia: evaluation using isotropic high-resolutional CT arthrography with sequential radial reformation. Osteoarthritis Cartilage. 2007 Mar;15(3):251-7.
- Henak CR, Abraham CL, Anderson AE, Maas SA, Ellis BJ, Peters CL, Weiss JA. Patient-specific analysis of cartilage and labrum mechanics in human hips with acetabular dysplasia. Osteoarthritis Cartilage. 2014 Feb;22(2):210-7.
-
Su T, Chen GX, Yang L. Diagnosis and treatment of labral tear. Chin Med J (Engl). 2019 Jan 20;132(2):211-219.
- Hartig-Andreasen C, Søballe K, Troelsen A. The role of the acetabular labrum in hip dysplasia. A literature overview. Acta Orthop. 2013 Feb;84(1):60-4.
-
Savoye-Laurens T, Verdier N, Wettstein M, Baulot E, Gédouin JE, Martz P. Labral tears in hip dysplasia and femoroacetabular impingement: A systematic review. Orthop Traumatol Surg Res. 2023 Jun;109(4):103539.
-